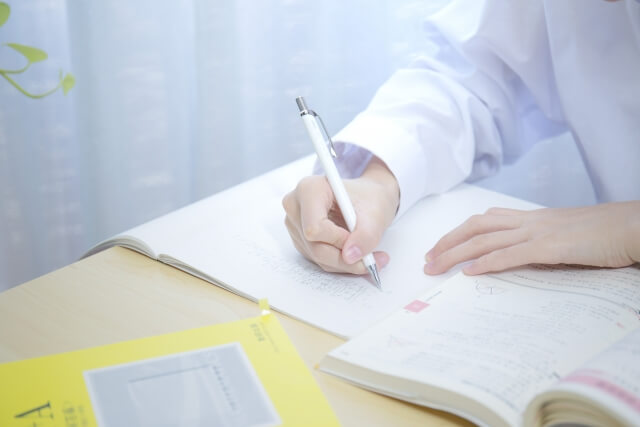成績がビリで学校生活への意欲も喪失している高校生が、あるきっかけから大学進学を目指し、急速に偏差値をあげて難関大学に合格するという物語があります。これを物語ではなく、現実にする 大学受験 の 勉強法 を紹介します。
難関大学合格者に共通する大学受験の勉強法の秘密
- 目次 -
そのはじまりは禁じ手から
高校2年生の夏休み、宿題として数学のテキストが配られた時、A君は、その日のうちに答えを丸写ししました。数学が苦手で、いつも期限までに提出ができず、怒られてばかりだった彼のやむにやまれぬ行動でした。
その代わり、A君は夏休み中「なぜこの答えになるか」をすべての問題について考えました。答えを出すことは苦手だけど、解き方を考えることはとても楽しかったという彼は、夏休み明けの課題テストでいきなり上位に入ります。これがはじまりでした。
キーワードは「なぜこの〇〇になるか」
解き方を考える楽しさを知ったA君は、この方法で英語を攻略します。
原文と訳文とを最初に写し、比較しながら「なぜこの日本語訳になるか」を、辞書と文法書を手に考えたのです。
最初は、文末が「~た(過去)」と日本語訳されているのは、英文の動詞の時制が「過去」になっているからというスタートでした。
しかし、このようにすべての言葉を丁寧に考え、英文と日本語訳とを結び付けていった結果、「英語が、数学と同じような論理的なルールの積み重ねによってできあがっていること」に気付きます。
そして、冬休み明けの課題テストでは、英語でも上位に入ります。
そしてA君の快進撃がはじまる
他の教科でも、「なぜこの〇〇になるか」を考えました。
古文・漢文では「なぜこの現代語訳になるか」、化学や物理では「なぜこの数値になるか」を徹底的に考えました。考え続けているうちに、単語・文法、公式・法則などを憶えてしまいました。
暗記が苦手だったA君ですが、なぜを考えるうちに、教科ごとに必要な知識は自然と身についてしまったのです。気が付けば、模擬試験の成績が安定し、得意教科、苦手教科という意識もなくなっていました。
どうしても解けない問題への対応
A君の成績はだいたい真ん中。模擬試験では白紙答案の提出もありました。
そんなA君は、白紙答案だった問題の勉強方法として、模範解答を繰り返し写すことをはじめました。繰り返し模範解答を写しているうちに「なぜこの答えになるか」がだんだんわかってくるのです。
こうして解き方のレパートリーを増やしていった結果、白紙答案はなくなっていきました。ちなみに、A君はこの作業を「写経」と呼んでいました。
難関大学合格者に共通すること
A君の勉強法は、多くの難関大学合格者と共通します。それは、正解か不正解かという「結果」よりも、正解に至る「過程」を重視し、正解とその理由の「一致」を求める傾向です。
彼らにとって「正解」と「なぜこの正解になるかの説明」とは、常にセットでなければならないものなのです。このこだわりが、難関大学合格者に共通する傾向です。
そんなA君、部活動引退後は部活動に費やしていた時間をすべて「考える時間」に注ぎ込みました。結果、偏差値は右肩上がりとなり、本人も絶対無理と思っていた難関大学に、見事現役で合格しました。
大学受験の勉強法は「論理的思考力」を身に付けることにある
大学受験の勉強法を「なぜこの答えになるか」の自問自答から初めてみてください。そして「答え」と「その理由」とが一致するまで思考を積み重ねてください。
このA君の大学受験の勉強法は、大学が受験生に求めている「論理的思考力」を鍛える方法なのです。ここに、A君の成功の秘密があります。またこれが、ビリから難関大学合格に導く先生たちの指導法でもあるのです。
まとめ
難関大学合格者に共通する大学受験の勉強法の秘密
論理的思考力
考える楽しさ
ビリギャル
偏差値の上昇
なぜこの答えになるか